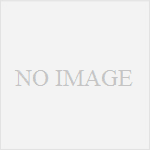「時計の読み方をどう教えたらいいのかわからない…」
そんな悩みを抱える親御さんや先生も多いのではないでしょうか。
- アナログ時計を見ても混乱してしまい、なかなか読み取れない
- 教えてもすぐに忘れてしまい、自信をなくしてしまう
- 教材や方法を試しても、どれもしっくりこない
時計の読み方は、日常生活に直結する大切な力。でも、発達障害のある子どもにとっては、抽象的で難しいスキルのひとつです。うまく伝わらないと、お互いにストレスになってしまうことも。
そこで本記事では、**実際の支援現場や家庭でも活用できる「具体的なステップ」と「楽しく学べる教材・工夫」**をご紹介します。
この記事を読むことで、子どもが「わかった!できた!」と感じられる関わり方や教材選びのポイントが見えてきます。
答えは、“焦らずステップを踏むこと”と“成功体験を積ませること”です。
発達障害の子が時計を読むのが苦手な理由とは?
数字や時間の概念が抽象的で理解しにくい
発達障害の子どもにとって、数字や時間という概念は非常に抽象的です。「5分がどれくらいか」「10時と14時の違い」など、目に見えないものをイメージするのは難しいと感じる子が多くいます。
特に「今から○分後」「あと何分」などの表現は、時間の流れや長さの感覚を伴います。こうした抽象的な思考は、一般的な発達よりも習得に時間がかかるケースがあるため、焦らずサポートすることが重要です。
短針・長針の役割がわかりづらい
時計には短針と長針があり、それぞれが意味することが異なります。ですが、針が動く様子を見ても「どうして長い方が“分”なの?」「短い針が“時間”なのはなぜ?」という疑問を抱く子は多くいます。
また、「6時半」のように短針がちょうど数字を指していない状態では、さらに混乱が起こりやすくなります。まずは短針と長針がそれぞれ何を示しているのか、役割を丁寧に理解させることが大切です。
脳の特性によって視覚・空間認識が難しい場合もある
発達障害のある子どもには、視覚認知や空間認知に困難を抱える子がいます。時計の針の角度や数字の配置は、そうした子にとっては「なんとなく見えにくい」「位置関係が分かりにくい」ことも。
また、アナログ時計は「12がてっぺん」「6が下」という空間認識が必要です。こうした感覚が育っていないと、どこをどう見たらいいのかが分からず、全体が意味不明に感じられてしまいます。
時計の読み方を教える前に大切なこと
子どもの発達段階を正しく把握する
「うちの子はもう◯歳だから、時計くらい読めるはず」と思ってしまいがちですが、実際には年齢よりも“理解の段階”が大切です。
時計の読み方は、数字の認知・時間の感覚・空間認知など、さまざまなスキルが複合的に関わっています。まずは子どもが「何がわかっていて、何が難しいのか」を見極めることから始めましょう。
親や先生が「焦らない」ことが成功のカギ
時計は毎日使うものだからこそ、早く読めるようになってほしいという気持ちは自然です。でも、その気持ちが子どもにとってはプレッシャーになることもあります。
「どうしてできないの?」「何回も教えてるでしょ!」といった声かけは、学ぶ意欲をそいでしまう原因になります。大切なのは、今の理解に寄り添いながら、少しずつ成功体験を積ませることです。
「できた!」を増やすためにハードルを下げる
最初から“完璧に読める”ことを目指すのではなく、段階的に「できた!」を増やしていくことが大切です。
たとえば、「○時だけが読めるようになる」「長針が6を指していたら“半”と覚える」など、成功体験を積み重ねるステップ設計を意識しましょう。ハードルを下げることで、自信とやる気が育ちます。
発達障害の子に効果的な時計の教え方ステップ
① まずは「○時」だけを覚える
アナログ時計を読む最初のステップは「○時」を理解することです。短針がどの数字を指しているかだけに注目し、「今は2時だね」などと声をかけて、時間の感覚をつかませましょう。
この段階では長針を無視して構いません。「短針=時間」のルールを定着させることに集中します。
② 「○時半」→「○分」の順に進める
「○時」が読めるようになったら、「○時半」へステップアップしましょう。ここでは長針が6を指すと「半」となることを伝えます。
その後、5分刻みで「5分、10分、15分…」と段階的に学んでいきます。このとき、実際の時計を動かしながら学習することが効果的です。
③ デジタル時計とアナログ時計をつなげて理解させる
デジタル時計の数字は直感的で分かりやすいため、アナログとの橋渡し役にぴったりです。
「この数字(デジタル)は、アナログだとこう見えるよ」と並べて使うことで、両者の対応関係が視覚的に理解しやすくなります。
④ 時計と生活をリンクさせる習慣づけ
「ごはんは6時」「寝るのは8時」など、生活の中で時計と行動を結びつけることで、時間の意味が実感できるようになります。
おうちの中にアナログ時計を増やしたり、「○時になったら〇〇しようね」といった声かけをすることで、自然と時間の感覚が育っていきます。
楽しく学べる!おすすめ教材・アプリ・絵カード
視覚支援に役立つ絵カードの使い方
絵カードは、視覚優位な子どもにとって非常に有効なツールです。
「2時=おやつ」「7時=おふろ」など、生活と時間を結びつけたカードを使うことで、時計の意味がイメージしやすくなります。毎日使うことで、徐々に定着していきます。
実際に効果があったおすすめ時計教材3選
- くるくる回せる知育時計ボード:針を自由に動かせて練習に最適
- 100均のホワイトボード式時計カード:親子でお絵かきしながら楽しく学べる
- こどもちゃれんじ かけるくん時計:遊びながらステップ学習が可能
ゲーム感覚で学べるスマホ・タブレットアプリ
- 「とけいであそぼう」シリーズ(iOS/Android):時計を合わせるパズルゲーム
- 「Time Teacher」:クイズ形式で読み方を練習できる
- 「とけいのよみかた」アプリ:日本語対応でわかりやすい音声付き
子どもの自信を育てる関わり方のコツ
成功体験を意識的に作る声かけの工夫
「すごいね!2時がわかったね!」など、できたことに目を向けて褒める声かけを積み重ねることで、子どもの自己肯定感が育ちます。
ミスに目を向けるより、小さな「できた」を見つけて一緒に喜ぶことが何よりのモチベーションになります。
「できない」ではなく「今は途中」と考える
読み方をすぐに覚えられないと、つい「この子には無理かも…」と思ってしまうことも。でも、スキルの習得には**「今はその途中にいるだけ」**と考える視点が大切です。
子どもの力を信じて、じっくりと育てていきましょう。
他の子と比べず、マイペースで見守る
ついつい「同じ年の子はもう読めるのに」と比べてしまいがちですが、それは親の焦りにつながります。
時計の理解には個人差があって当然です。子ども自身のペースを尊重して見守ることが、安心して学ぶ土台になります。
まとめ│楽しみながら、少しずつ時計に親しもう
発達障害のある子どもにとって、時計の読み方は簡単なことではありません。でも、段階的に教え方を工夫することで、必ず「できた!」を実感できる瞬間が訪れます。
大切なのは、焦らずステップを踏むこと、そして子どもの成功体験を積み重ねていくことです。
絵カードやアプリ、知育教材などを活用しながら、子どもの得意な方法で楽しく学べるようにサポートしてあげてください。
今日からでもすぐに始められる工夫ばかりです。ぜひ一つでも試してみて、子どもと一緒に「時計がわかった!」という笑顔の瞬間を増やしていきましょう✨
| ★楽天1位【改良版】目覚まし時計 子供 知育目覚まし時計 知育時計 アラーム 学生 寝室 可愛い 3色 おしゃれ アナログ 卓上時計 ライト 置き時計 北欧 シンプル 連続秒針 静音 寝室 起きれる 日本語表示 新生活新学期 勉強入園 入学 価格:2,280円~(税込、送料無料) (2025/4/16時点) 楽天で購入 |
| うんこドリル とけい 5・6さい (幼児 算数 時計 5歳 6歳) [ 文響社(編集) ] 価格:1,078円(税込、送料無料) (2025/4/16時点) 楽天で購入 |
| はじめてのとけい (幼児ドリル かず・けいさんシリーズ) [ くもん出版編集部 ] 価格:726円(税込、送料無料) (2025/4/16時点) 楽天で購入 |