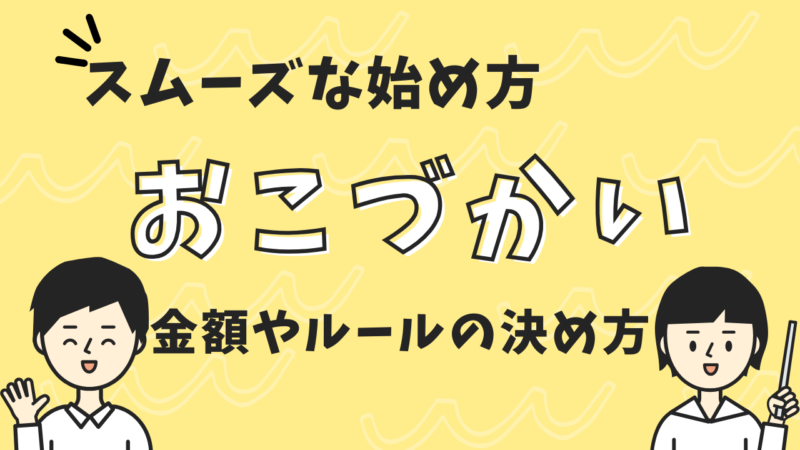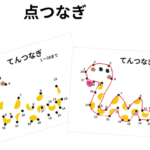「おこづかいっていつから始めるのがいいの?」「金額はどれくらい?」「どんなルールを決めればいいの?」
お子さんのおこづかいについて悩む親御さんは多いのではないでしょうか。おこづかいは、金銭感覚を養い、将来の金銭管理能力を育てる大切なステップです。本記事では、おこづかいを渡すタイミングや金額の目安、ルールの決め方について詳しく解説します。
おこづかいを渡すタイミングの目安
おこづかいを始める時期は子どもによって異なりますが、以下のタイミングを目安に考えてみましょう。
・お金に興味を持ち始めたとき
・物をお金で買うことを理解したとき
・「欲しいもの」ができたとき
一般的には、早ければ幼稚園の年少・年中から始められることもあります。遅くとも小学校高学年には導入しておくことで、金銭管理の基礎を身につけることができます。
おこづかいの種類と特徴
おこづかいの渡し方には、主に以下の3つのタイプがあります。それぞれの特徴を押さえた上で、家庭に合った方法を選びましょう。
1. 定額タイプ
一定の金額を週や月単位で渡す方法です。
・メリット
子ども自身が計画的なお金の管理を学べる
・注意点
おこづかいの使い道ルールを明確にしておく必要がある2. 報酬タイプ
お手伝いや努力に応じておこづかいを渡す方法です。
・メリット
働くことの大切さを学べる
注意点
「働かないとお金が手に入らない」といった偏った考えが生まれる可能性がある
3. ミックスタイプ
定額タイプと報酬タイプを組み合わせた方法です。例えば、基本的な定額のおこづかいに加え、特別なお手伝いをした場合に報酬を追加するなど、柔軟な運用が可能です。
おこづかいのルールを決めるポイント
おこづかいを渡す際には、以下のようなルールを設定しておくとスムーズです。
1. 購入するものの範囲を決定する
生活必需品(文房具や学校用品)は親が負担し、趣味や嗜好品はおこづかいで購入するなど、明確な線引きをしておくと子どもにも分かりやすくなります。
2. お金の使い道を分類する
おこづかいを以下の3つに分類すると、計画的な使い方を学べます。
・自由に使えるお金
・貯金
・「ありがとうのお金」
「ありがとうのお金」とは、募金や誕生日プレゼントなど、人のために使うお金のことです。小さい頃から「人に感謝するお金」の使い方を学ぶことで、豊かな心を育むきっかけになります。
おこづかいの管理方法
おこづかいを渡すだけでなく、管理の仕方も教えるとより効果的です。ツールの活用例
・計画書: 何に使うか計画を立てる
・おこづかい帳: 入出金を記録する
・簡単な契約書: 家族でルールを明文化し、お互いに確認する
お金の使い方を考える習慣を育てる
お金の使い方には、以下の3つの種類があります。
・浪費: なくても困らない贅沢品
・消費: 生活に必要なもの
・投資: 自分の成長や未来に役立つもの
例えば、「本を買う」場合、読む意図がなく無計画であれば浪費となり、読んで知識を得られるなら投資となります。買い物の際に「これは本当に必要?」「浪費か投資か?」と子どもと一緒に考える時間を持つことで、判断力を育てることができます。
まとめ
おこづかいは、子どもに金銭感覚や管理能力を教える大切な機会です。「ありがとうのお金」やおこづかい帳を活用し、楽しみながら学べる工夫をしてみてください。
ぜひこの記事を参考に、家庭に合ったおこづかいルールを作ってみてくださいね!