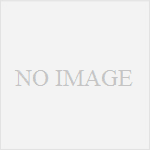「困っても誰にも言えずに、黙り込んでしまう」
- 「助けてって言えないから、誤解されてしまう」
- 「一人で頑張らせすぎて、子どもも自分も疲れてしまう」
発達に特性がある子どもを育てていると、こうした悩みに直面することがあります。
自立を促すつもりが、かえって子どもを追い詰めてしまう。そんな経験をされた方も多いのではないでしょうか。
今、注目されているのが「受援力(=助けを求める力)」です。
そして「アントレプレナーシップ(=挑戦し、自分らしく生きる力)」と組み合わせて育てることで、
子どもが社会の中で自分らしく生きていく力を身につけることができます。
本記事では、発達に特性のある子どもが「助けて」と言えるようになりながら、自立への一歩を踏み出せるよう、
家庭や学校でできる具体的な関わり方を紹介します。
この記事を読むことで、子どもの将来の力を育てるヒントが見つかります。
そして「自立」と「支え合い」が両立できる、新しい子育ての視点が得られます。

結論:受援力とアントレプレナーシップは、子どもが自分らしく社会で生きていくために、どちらも欠かせない力です。
アントレプレナーシップとは?子育てに必要な理由
アントレプレナーシップ=自分の人生を切り開く力
アントレプレナーシップとは「起業家精神」と訳されることが多い言葉です。
しかし、本来の意味は「自ら課題を見つけ、価値を生み出す行動力」のこと。
これは起業に限らず、すべての人に必要な「自分らしく生きる力」といえます。
子どもにとってのアントレプレナーシップとは、「やってみたい」「工夫したい」「自分で選びたい」と思える心です。
そしてその思いを行動に移す小さな一歩を積み重ねることです。
なぜ今、子どもにアントレプレナーシップが必要なのか
AIや自動化が進むこれからの時代には、「指示を待つ」だけでは生き抜けません。
正解がない問題に、自分の頭で考え、答えを出す力が求められます。
そのためには、失敗を恐れず挑戦する心や、自分の意見を言う勇気が必要です。
まさにアントレプレナーシップは、これからの社会に必要不可欠な力といえます。
発達特性のある子どもにこそ必要な視点
発達に特性のある子どもは、周囲との違いに悩んだり、自己肯定感が下がりやすい傾向があります。
しかし、見方を変えれば、独自の視点やこだわり、柔軟な発想こそが強みです。
だからこそ、その子らしい価値を活かす「アントレプレナーシップの芽」を育てることが大切です。
受援力とは?困ったときに「助けて」が言える子に育てる
「助けて」が言える=社会で生き抜く力
受援力とは「支援を受ける力」、つまり「助けて」と言える力のことです。
日本では「一人で頑張ること」が美徳とされがちですが、現代社会では「適切に助けを求められること」が重要です。
受援力のある子は、自分の状態を把握し、必要なときに必要な人に助けを求められます。
これはストレスへの耐性を高め、社会での適応力を育てる土台になります。
受援力を育てると起きる3つの変化
- 自分の気持ちや困りごとに気づけるようになる
- 他者との関係性が柔らかくなり、トラブルが減る
- 安心できる環境の中で挑戦がしやすくなる
受援力は、単に「頼る」ことではありません。
自分の感情やニーズを言葉にし、相手との関係を築く大切なスキルです。
甘えとの違いをどう伝える?
「助けて」と言うことは、決して甘えることではありません。
むしろ、自分の力を最大限に発揮するための戦略です。
この違いを伝えるには、「困ったときに相談するのはかっこいいことだよ」と肯定的に伝えることが効果的です。
親自身が「今日は疲れたから助けてね」と子どもに伝えることも、受援力のモデルになります。
アントレプレナーシップと受援力はセットで育てよう
一人で頑張るより「助けを借りて挑戦する」が現代的
アントレプレナーシップは「挑戦する力」、受援力は「助けを借りる力」です。
一見、対極にあるように見えますが、実はこの2つは補い合う関係にあります。
どんなに挑戦心があっても、周囲と関わりながら進める力がなければ、壁にぶつかったときに孤立してしまいます。
だからこそ、「助けを借りながら挑戦する力」が、これからの社会で必要なのです。
支援に頼る力が自立につながる理由
「自立」とは、なんでも一人でできることではありません。
必要なときに適切な支援を受けながら、自分の意思で選び、行動することです。
受援力を持つ子は、適切に人と関われるので、社会との接点を持ちやすくなります。
結果的に、孤立せずに自分らしい道を切り開いていけるようになります。
家庭や学校でできるバランスのとれた支援の考え方
大人ができることは、「全部やってあげる」でも「突き放す」でもありません。
子どもが困ったとき、「どうしたい?」「どこまで自分でやってみる?」と問いかけることで、
挑戦と支援のバランスを自然に育てることができます。
日常でできる!力を育てる5つの関わり方
①失敗しても大丈夫というメッセージを伝える
挑戦には失敗がつきものです。
「失敗しても大丈夫」「やってみてえらいね」と、結果よりも過程を評価しましょう。
この安心感が、挑戦する力=アントレプレナーシップの土台になります。
②挑戦を応援する環境づくり
子どもが「やってみたい」と言ったことは、できる範囲で実現してあげましょう。
お金をかけなくても、道具を用意したり時間を確保するだけでも十分です。
挑戦を尊重することが、子どもの意欲につながります。
③助けを求めることを「強さ」として伝える
「助けを求められることは恥ずかしくない」「困ったときは相談していいんだよ」と繰り返し伝えてください。
絵本やアニメなどの登場人物を使って伝えるのも効果的です。
④親や先生も「受援力」を実践する
大人が自分の限界を認め、人に頼る姿を見せることで、子どもも「頼っていい」と理解します。
「今日はちょっと疲れてるから手伝ってくれる?」という一言が、立派な受援力のモデルです。
⑤子どもの「選ぶ力」を育てる問いかけ
「今日はどの服がいい?」「どのおやつにする?」など、小さな選択を子どもに任せましょう。
選ぶ経験の積み重ねが、自分の人生を自分で選ぶ感覚につながります。
まとめ|自分らしく、支え合いながら生きる力を育てよう
アントレプレナーシップ(挑戦する力)と受援力(助けを求める力)は、どちらもこれからの時代を生きる子どもにとって重要なスキルです。
特に発達に特性のある子どもにとっては、自分らしく自立していくための大切な土台になります。
今日からできる小さな関わりが、子どもの「生きる力」を大きく育てていきます。
ぜひ、日常の中で声かけや関わり方を少しだけ意識してみてください。
「困ったときは助けてもいい」「挑戦していい」
そんな安心感のある環境が、子どもを前向きに成長させてくれます。